葬儀社を比較検討するときどのような手順と方法で決めるかご存じでしょうか。
ほとんどの方が「検索したり口コミを見れば大体わかる」とお思いではないでしょうか。
ですが、いざ下調べなしに葬儀社を選ぶと後々後悔することもあります。
実際にご葬儀を経験した方の後悔している原因として「事前の情報収集が不足していたこと」をあげています。
このコラムでは、初めて葬儀の喪主になる方でも葬儀社をちきんと選びイメージ通りのお葬式を実現するために、事前に押さえておくべきポイントを5つに絞って解説しています。
ポイント1:送り方を決めて、家族と共有しよう
葬儀社を決めるために最初に行うべきことは「どのような形式で葬儀を行うか」です。
葬儀社やプランを決める前に「送り方」が決めておくとスムーズに進められます。ここでは葬儀を検討する方が最初に行うべき葬儀の形式の決め方について解説します。
葬儀の「形式」を決める
送り方を決めるためには、葬儀の形式を決めることから始めましょう。葬儀の形式の種類は大きく分けて4つあります。
形式1:直葬
直葬とは宗教者を招かず、家族や近しい親戚だけでお別れをするシンプルな葬儀です。
「直葬」「火葬式」「お別れ式」など、様々な呼び方がありますが、ご遺体が安置されている霊安室で故人を棺に納め、花入れ(献花)をして火葬場に向かう点がことです。
なお、近年は直葬の中でも「お別れの機会」すら省いた「超直葬」も定番化しています。
「超直葬」は10万円を切る低価格設定になっていることが多く、ご遺体を預けた後は原則として火葬まで故人と面会することはできません。
火葬当日も火葬炉の前で数分故人の顔を眺めるだけで、じっくりとお別れをする時間が取れないので理解しておきましょう。
直葬のメリット
・費用が抑えられる
直葬形式は祭壇や式場といった「儀式に伴う基本費用」がかかりません。また、通夜を行わないので通夜振る舞いなど接待費用も最小限に抑えることができます。宗教者の手配も必要がないため住職に渡すお布施や戒名にかかる費用も不要です。
・喪主の負担が少ない
直葬は会葬者が少ないため通常の葬儀に比べ事前準備が少なくて済みます。供花のとりまとめや関係者への連絡もしなくていいので負担が少ないです。当日も葬儀担当者との打ち合わせはほとんど必要がなくお別れに集中できます。
直葬は参列してほしい人への連絡以外は、自分たちの準備に時間を使うことができます。近しい親戚しか来ないため気を遣わずに故人とのお別れに集中できます。
直葬のデメリット
・菩提寺に認められないことがある
菩提寺がある場合には、直葬を行うことを認めてもらえない場合があります。戒名を授け、仏弟子として送り出すことが菩提寺としての務めです。菩提寺にお伺いを立てず直葬を行うことはできません。
・終わった後から苦言をいただくことがある
直葬は基本的にごく限られた家族を中心に行います。そのため故人と縁のあった友人知人のお別れの機会を奪うことになってしまいます。さらに、故人の交友関係が広い場合、葬儀後にひっきりなしに弔問客きて落ち着かないことがあります。特に会社に長く貢献していた方だった場合、中には「なぜちゃんと葬儀を行わなかったのか」と苦言頂くこともあります。
・ちゃんと送ってあげられたか不安になる
直葬は儀礼儀式のような作法やしきたりのない自由な形で行われます。シンプルがゆえに「本当にこれでよかったのだろうか」と不安になることがあります。
実際に直葬であげたものの後悔して、一周忌で読経を依頼された方もいます。
形式2:一日葬
一日葬とは通夜を行わず告別式のみを1日で行う形式です。一日葬は直葬ほど簡易的ではなく、従来のよりも体力的に負担がすくないため近年増えています。お布施も1日分で済むことから、菩提寺がないが仏式で送りたい方から支持されています。
一日葬のメリット
・参列者の負担を抑えることができる
家族や身近な親戚は原則として通夜にも参列することとなります。しかし両日とも参列するのはお年寄りや体の不自由な方にとって負担となります。さらに、遠方から参列してもらう場合は宿泊場所の手配も必要になります。一日葬の場合は1日ですべて終えることができるため、参列者の負担が軽減できます。
・儀式を通じ「送った実感」が得られる
直葬も1日葬も、1日で完結するという意味では似ています。
しかし1日葬は基本的に読経などの儀礼儀式を通してしっかりと送ることができるので、後悔することが少ないといえます。
通夜がないため前日まで葬儀の準備に時間を費やすことができます。
一日葬のデメリット
・1日の拘束時間が長く、あわただしい
一日葬では本来通夜に行う納棺式を葬儀の前に。また、供花の並び順や席順の確認などすべて葬儀当日に行います。1日にやらなくてはならないことが集中するので、集合時間も通常の告別式よりも早くなります。朝早く出発し、火葬が終わり自宅に帰ることには日が暮れているなんてことも珍しくありません。
・費用は2日で行うときと大きく変わらない
2日で行う形式と一日葬とでは、基本費用はほとんど違いがありません。式場使用料も使用日数で金額設定を変えていない式場も多く、必要な設営にもほとんど違いはありません。確かに葬儀社の人件費1日分程度の軽減されます。しかし、忙しくなるわりに費用負担はほとんど変わらないのがデメリットと言えます。

一日葬の流れやスケジュールについて詳しくは
形式3:2日葬(通夜・告別式を行う形式)
2日葬は通夜と葬儀を行い故人を送り出す、一般的なご葬儀形式のことを言います。10年ぐらい前まではほとんどが2日かけて行う葬儀でした。
一般的な葬儀から外れたことをしたくないという方や、より多くの方にお別れの機会を作ってあげたいと思う方が選ばれる形式です。
2日葬のメリット
・会葬者が参列しやすい
通夜と葬儀の2日間にかけて行われますので、日中仕事や学校があっても参列がしやすくなります。より多くの方にお別れの機会を提供できることがメリットと言えます。
・故人と家族がより深く故人を偲ぶことができる
葬儀の日はは「火葬」という制限時間があります。ゆっくりと故人を偲びたくても時間には限りがあります。しかし通夜は葬儀と違い時間を気にせず故人の思い出話に花を咲かせることができます。また、通夜振る舞いの席を通じてお世話になった方々から家族も知らなかった故人の一面を知ることができたるため深く故人を知り偲ぶことができます。
2日葬のデメリット
・体力的に負担が大きい
宿泊をするにせよ、自宅に帰るにせよ、体力的に休まらないということがあげられます。
特に逝去後は睡眠をとれていない家族も多いです。通夜と葬儀の2日間をかけて葬儀を行うことは体力的に負担になるといえます。
・費用の負担が増える
一日葬と比較して基本費用は大きく変わりません。しかし通夜振る舞いをする場合には2日間行う方が費用の負担が多くなります。
おもてなし費用は香典と相殺され実費はそこまでかかりません。しかし足りなくならないように料理を多めに注文してしまい、実費負担が増えてしまうこともあります。料理は返品がきかないので、担当者と相談して決めましょう。事前相談の細かく決めておく必要は
形式4:密葬&お別れ会
密葬とは後日お別れ会を行うことを前提に小規模に執り行われる葬儀のことです。密葬だからといって直葬でなければいけないことはありません。
お別れ会は企業の代表や創業者、芸能人や文化人などの著名人が行うことが多い葬儀形式です。お別れ会は多数の参列者が予想されることや準備に時間がかかることもあり、執り行うまでに数か月要することもあります。すでに遺骨になった状態で執り行われるため、葬儀式場だけでなくホテルやイベント会場、会社など会場をどこにするかは比較的自由に選ぶことができます。
どこまで声をかけるか決めよう
葬儀の形式を決めたら、どこまでの方に声をかけるかを考えましょう。
なぜ声をかけられなかったのか聞かれてもきちんと理由が説明できるよう明確に線引きをしましょう。そうすることで参列する側も断られた方も納得ができます。事前に理由伝えておかないと呼ばれなかった親戚と関係が悪化する可能性があります。
ここでは声をかける範囲を制限することで考えられるメリットデメリットについて解説します。
・家族や親せきだけで行う
メリット
喪主が自身のお別れに集中できる
家族だと親戚だけで行うメリットは、参列者に気を遣うことなく喪主も家族の一員としてお別れに集中できることです。静かに故人と最後の時間を過ごすことができるので、十分なお別れをすることができます。
デメリット
葬儀後に弔問対応に追われることがある
葬儀当日は身近な親族だけでゆっくりとお別れができます。その反面、故人と生前から親しくしていた友人や会社関係者に十分なお別れができなくなります。
故人の交友関係が広い場合や、故人が会社を引退して間もない場合は、葬儀が終わってからもしばらく弔問客が自宅に来ることがあります。対応に追われ自宅を留守にしにくくなり、葬儀後の手続きがなかなか進まないなど、落ち着かない日々が続くことが考えられます。
・友人や会社関係者までもれなく声をかける
メリット
知らなかった故人の人となりを知ることができる
様々な方が参列する様子を見て改めて故人のご縁に気づかされます。また、参列した方と話をする中で、家族の前では見せない故人の意外な一面を知る機会にもなり、より故人への想いを深めることができます。
デメリット
参列者対応に追われ自分のお別れが十分にできない
参列者が多いと受付の手配や供花や席の順番など担当者と打ち合わせることが増えます。また、参列者向けに対して挨拶をしなくてはならないので、気を遣ったり緊張する場面が多く、故人を偲ぶ時間を十分に取れない可能性があります。
家族と親戚に伝えておく
葬儀の形式と声をかける範囲を決めたら他の親せきにも共有しましょう。もしかすると全く違う考え方を持っているかもしれません。いざ葬儀が発生してから身内に反対されるのはつらいものです。どのような送り方をするか、家族の考えや想いを伝えておくとスムーズです。
ポイント2:葬儀社の種類を知ろう
送り方が決まったら、その送り方の葬儀を得意としている葬儀社を選びます。一言で葬儀社と言っても運営組織や会社の規模が異なる場合があります。
ここでは葬儀社にはどのような種類があるのか、葬儀社の種類について解説します。
葬儀社は大きく分けて3種類
・葬儀専門業者
葬儀の専門業者は葬儀社として創業し、ご葬儀に特化した高いサービス力が特徴です。会員制度を設けている場合が多いですが、ほとんどの場合数千円~1万円程度の入会金のみで割引の適用を受けることができます。地元で長く葬祭業を行っている会社が多く、その地域でのご葬儀経験が豊富です。
代表的な葬儀社
・公益社(本社:東京都港区)
・ティア(本社:愛知県名古屋市)
・お葬式のむすびす(本社:東京都江戸川区)
・互助会系葬儀社
互助会とは加入者が毎月一定の掛け金を前払い金として払い込むことにより、冠婚葬祭の儀式に対するサービスを受けることができるシステムです。月々数千円の少額の積み立てで数十万円の葬祭サービスが受けられるメリットがあります。
また、会費を斎場の設立や運営資金に利用して充実した設備やサービスを安定供給できる体制も互助会ならではの特徴と言えます。
代表的な互助会系
・ベルコ(大阪府池田市)
・メモワール(神奈川県横浜市)
・日本セレモニー(山口県下関市)
・葬儀社紹介サイト
葬儀社紹介サイトは葬儀社ではなく、希望のエリアで要望に応えられる葬儀社を紹介してくれるサービスです。葬儀自体を行うわけではないので厳密には葬儀社ではありません。
実店舗を持たずにインターネットを中心に集客を行うのが特徴で、葬儀施行にかかる固定費が不要なので、低価格かつ全国一律の金額で葬儀を行うことができます。
代表的な葬儀社紹介サービス
・小さなお葬式(大阪府大阪市)
・よりそうお葬式(東京都品川区)
・やさしいお葬式(東京都港区)
ポイント3:3社から見積もりを取り比較しよう
葬儀の形式と呼ぶ範囲を決めると、式場と選ぶべきプランが見えてきます。ここまで決まれば葬儀社に見積もりを取るために必要な情報が揃います。
葬儀で後悔しないために最も大切なのは葬儀社選びで失敗しないことです。
葬儀を検討している地域の葬儀社を調べ、利用者のクチコミや立地、会場の雰囲気などを見て気になる葬儀社を3社程度に絞りましょう。
なぜ3社必要なのか
見積もりはできるだけ3社取るようにしましょう。1社では比較対象がないため適正かどうかがわかりにくく判断ができません。3社集めることで見積もり内の共通項目や葬儀社独自の項目がわかります。違いを知っていれば、見積もりについて問い合わせるときもポイントを絞ってより質問ができます。
見積書を依頼するときにつたえること
葬儀社として見積もりを作成すうえで最低限聞いておきたい情報がいくつかあります。問い合わせたときにスムーズに用件を伝え、条件に差が出ないように伝えるべき内容はあらかじめメモしておきましょう。
・葬儀を検討している市区町村
・おおよその参列人数(5~10名単位で構わない)
・宗教や宗派の有無(仏式、神式、無宗教、創価学会、など)
・検討しているプラン
・対象者の住所登録地
もしプランを決めかねている場合には「同条件で1日葬プランで行う場合と家族葬プランで行う場合の2パターンの見積もりをお願いします」と依頼すれば同条件でプランだけを変えた場合の見積もりを作成してくれます。
見積もりを比べるときは条件を合わせる
見積書が手元に届いたら事前に伝えたとおりの条件で作成されているかを確認します。もし比べてみた中でわからないことがあったら直接葬儀社に尋ねてみてもいいでしょう。
葬儀社の見積もりの比べ方がわからないという方のために、見るべきポイントについて解説します。
・条件を合わせる
まずは伝えたとおりの条件で作成されているか確認します。見積書に会食や返礼品などの人数に関わるオプションを含めている場合と、別途費用として含めていない場合があるので、同条件で計算されているかどうかを中心に確認します。
・商品の単価を確認する
「○○プラン」などとパッケージ化してプランを販売している葬儀社の場合、ドライアイスや霊安室の安置料金などの変動費をプラン内に含んでいる場合があります。ただし葬儀社によってプランに内包している日数が異なります。「必要なものはすべて含まれています」と説明されていたのに、実際には日程が延びたことで追加費用が発生し、トラブルに発展することもあります。
通常は変動する費用に関しては単価の記載があります。安置料であれば1日○万円、料理なら一人○千円といった形です。記載がない場合は葬儀社に確認しましょう。
・追加になる可能性がある項目を洗い出す
変動する可能性が高いのは「安置料金」「ドライアイス料金」「搬送料金」「返礼品代」「料理代」です。安置料金とドライアイス料金は基本プランに内包されているケースがありますので、何日分含まれているか見積書や資料を見て確認します。
搬送費用も何kmを超えると追加料金が発生するか距離を確認しておきます。また、搬送費用の場合会社によって出発地点が異なります。葬儀社の車庫から計算するか、病院出発地点から計算するかで追加料金が発生するかどうかが変わります。
返礼品や料理は、参列者に対するおもてなしであり、頂く香典と相殺される費用なので総額を気にする必要はありません。単価がいくらか、見積もりの単価が最低ラインなのか平均的なのか、料理メニューと見比べて確認しましょう。
・注釈を見落とさないように気を付ける
葬儀は行う会場により雰囲気がガラッと変わります。そしてパンフレットに使用されている式場写真やイメージ画像は見栄えのする式場で撮影していることが多いです。
画像の近くに「※写真はイメージです」などと注釈がある場合は、実際の会場ではない可能性が高いので施設見学をするか施設の画像が乗っている資料を請求するようにします。
また、追加料金が発生する条件も注釈として小さく書かれていることがあるので、よく見ておきます。
ポイント4:事前割引制度がないか確認しよう
葬儀社はほとんどの場合は会員制度や早割などのお得な特典を持っています。送られて送る見積書はおそらく会員価格適用時の金額で算出されているでしょう。
会員制度も無料のものから、毎月数千円を積み立てる制度など様々な種類があります。同じ場所で同じ内容の葬儀を行うならやはり安い方がいいですよね。
ここでは代表的な葬儀社の割引や会員制度をご紹介いたします。
割引制度の具体例(2025年1月現在)
例①:ティアの会(株式会社ティア:愛知県名古屋市)

株式会社ティアは愛知県名古屋市に本社を置く葬儀社です。入会金無料のブロンズ会員と入会金1万円のゴールド会員、東京都内限定のT会員の3種類の会員制度があります。
ゴールド会員だと通常の葬儀代より約7万円、無料のブロンズ会員でも約3万円お得になります。
例②:株式会社ベルコ(大阪府大阪市)
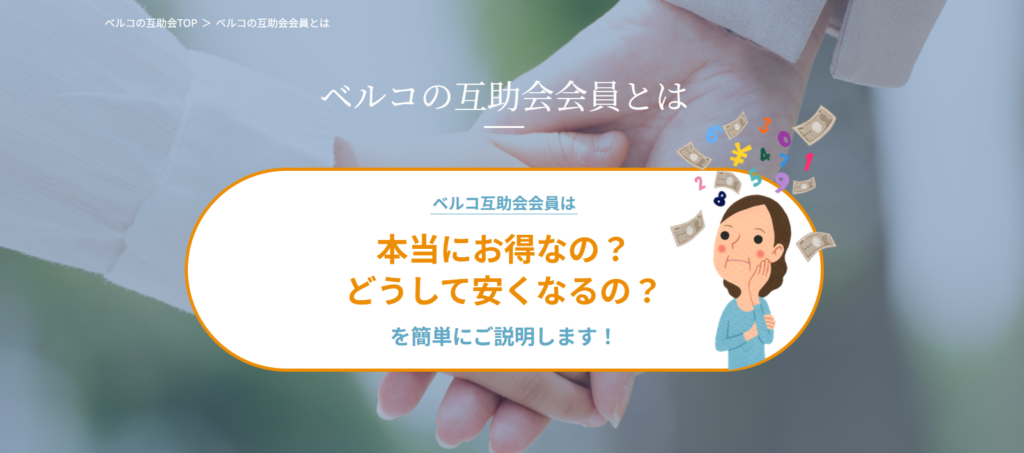
株式会社ベルコは大阪市に本店を置く大手互助会です。グループ傘下の葬儀社も入れるとほぼ全国で葬儀サービスを提供しています。ベルコの会員制度は「互助会」といいます。互助会とは将来の葬儀に備えるために毎月少額を積み立てておき万が一の費用負担を軽減するシステムです。地域によりコース内容は異なりますが、BEコースに加入している場合、会費を差し引いても通常価格より約20万円安くなります。
互助会は原則亡くなった後には加入できないので、早めに相談するとよいでしょう。
例③:小さなお葬式(大阪府大阪市)

小さなお葬式は株式会社ユニクエストが運営する葬儀社紹介サイトです。低価格かつ明瞭な金額設定、家族葬専門というブランドが支持され葬儀受注件数は全国1位となっています。TVCMも放映していたため知っている方も多いのではないでしょうか。
小さなお葬式はインターネットで集客をする会社ということもあり、資料請求をするだけで5万円の割引が適用されます。
実際の斎場を見学しよう
見学がなぜ大切なのか
葬儀社の見積もりを比較し、自分たちのやりたい葬儀がイメージ出来たら実際に施設を見学しましょう。斎場を見学すると会場の広さや雰囲気だけでなくスタッフの対応品質も見ることができ、本当に信頼できる葬儀社なのかがわかります。ここでは施設見学の重要性と見学時に見るべきポイントを解説します。
斎場見学で見るべきポイント
・立地や周辺環境
斎場の周辺に大きな商業施設があり車どおりが多く騒がしい、メインの通りから1本外れた場所にあるのでわかりにくい、などアクセス情報だけではわからない斎場の周辺環境をチェックしましょう。土地勘のある人目線ではなく参列者の目線でわかりやすい場所か、斎場に宿泊する場合は徒歩圏内にコンビニがあるかどうか、など参列したときをイメージして見学をしましょう。
・交通の便、駅の距離や駐車場
実際に斎場に足を運んでみると参列する際の不便さがよくわかりますまた、車で来る場合は十分な台数が確保できるかどうか、を確認しましょう。
火葬場までの距離とルートも確認すべき大切なポイントです。土地勘のない親戚が火葬場に行くときにはぐれたり迷ったりしないよう、火葬場から近い斎場を選ぶのも選択肢として残しておきましょう。
・広さと明るさ
パンフレットやホームページの画像と実際の式場の違うことが多々あります。これは画像を後から明るく加工したり、椅子の配置やレイアウトを変えているからです。思っていたよりも広い、暗いと感じることがあるため可能な限り現地を見学しましょう。
また、日中でも日が当たらずに暗く寒々しい雰囲気だったりすることもあります。
・式場以外の待機場所
式場だけでなく控室やロビーなどの「待機スペース」があるかどうかも重要です。
ドリンクコーナーやキッズスペースなどお迎えの姿勢が待機場所への配慮でわかります。
・スタッフの対応
施設見学をする際に一番大切なのは対応してくれるスタッフを見ることです。もし予約をして施設を見学する場合には早すぎず遅すぎず時間通りに行きます。外に出てお出迎えをしてくれるスタッフはおそらく丁寧に接客してくれます。
また、対応時のスタッフ身だしなみも重要です。ワイシャツで腕まくりで対応する職員は論外です。
他にも相談者によりそう姿勢や、専門用語を使わずに説明してくれるかどうかなど、葬儀社を評価できるポイントはたくさんあります。
まとめ
今回は後悔しない葬儀のために喪主が事前にするべきこと5選を解説いたしました。
・自分たちのイメージを明確にすること
・それを家族や親せきと共有すること
・自分たちのイメージする葬儀ができる葬儀社を見つけること
・実際に現地でイメージをさらに具体的にすること
これらを意識して葬儀社を選ぶことで「思っていたのと違う…」という失敗をする可能性がぐっと下がります。1度きりの葬儀で後悔することがないよう、ぜひ参考にしてみてください。
見積もりの比べ方がわからない方はサービスを利用しよう
葬儀のセカンドオピニオンでは、忙しくて葬儀社の情報を集めて比べる時間がない、資料請求したものの何をどう比べればいいかわからない、まだ具体的に葬儀社を決めていないのに名前や住所を伝えるのは不安、という方のために葬儀社情報の収集と比較を代行しています。
サービスは下記にて販売しておりますので興味がある方はメッセージをお願いします。



