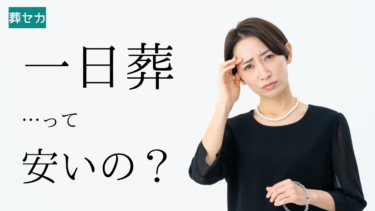一日葬とはどんな葬儀なのか
一日葬とはその名の通り通夜を行わず葬儀のみを行う葬儀の形式です。通常通夜・葬儀と2日間かけて行うものを1日で終えられるので喪主の負担も軽減することができます。
それでは一日葬はどのような流れで進行するのでしょうか。スケジュールに沿って一日葬の流れを解説します。
一日葬の流れ
逝去・安置
逝去されたら、まずは葬儀社に連絡し安置場所に搬送を依頼します。その際医師から死亡診断書を受け取り、安置場所まで持っていきましょう。自宅に安置する場合、家族は故人を寝かせる布団を準備します。葬儀社の霊安室に安置する場合は布団の用意は不要です。安置が整うまではスタッフの案内に従って待機し、声がかかったら順番に線香をあげお参りします。
打ち合わせ
安置が終わり一通りお参りが済んだら担当者との打ち合わせです。打ち合わせではまず日程を決めていきます。日程を決める際には①菩提寺の都合②式場の空き③火葬場の空きのどれが欠けてもいけません。特に菩提寺は替えがききませんので最初に確認しましょう。
日程が決まると棺や生花装飾など葬儀の内容を決めます。一日葬の場合、通夜料理の打ち合わせは行いません。全体のスケジュールも打ち合わせの時に決定します。通常一日葬では通夜の日に行う「納棺式」を葬儀の日に行います。しかし、葬儀の日にすべて盛り込むと集合時間が早くなったりあわただしくなります。ですので、納棺式は前日のうちに近しい家族だけで済ませてしまうのがおすすめです。担当者に伝えれば対応してもらえるので、遠慮せず聞いてみましょう。
納棺式
納棺式とは故人の遺体を棺に納める儀式のことです。一般的な仏式の場合は故人の体を清め旅支度をします。納棺式は近しい家族や親族が集まり行う儀式で、比較的少人数で行われます。通夜を行う場合は通夜式の2~3時間前に行いますが、一日葬の場合は葬儀の前に行わなくてはなりません。しかし葬儀の時間によっては集合が早朝になってしまい参列者の負担が大きくなります。同じ会場で前日に通夜が入ることがありませんので、前述のように納棺式は葬儀の前日に行うよいでしょう。
葬儀・告別式
葬儀の流れに関して一日葬と通常の葬儀に大きな違いはありません。読経が始まったら担当者の案内に従って順番に焼香をします。繰り上げ初七日法要を行う場合は葬儀閉式後に再度焼香を行います。読経終了後は柩に献花し、火葬場に向け出発します。
火葬・解散
火葬場に到着したら喪主から順に焼香し、火葬炉に納めます。火葬には約1時間かかるので、遺族は火葬場内の控室で待機します。一日葬の場合は精進落としを火葬中に行うことが多いため、控室に料理を手配します。火葬が終了したら収骨して解散します。
一日葬のスケジュール

一日葬の大まかな所要時間とスケジュールは以下の通りです。
| スケジュール | 所要時間 |
|---|---|
| 納棺式 | 30分~1時間 |
| 葬儀・告別式 | 1時間30分 |
| 火葬・収骨 | 1時間30分 |
それぞれのセレモニーの間には待機時間や移動時間などが入るため、集合から解散までおおよそ5~6時間程度かかります。9時集合だと仮定すると、9時~10時に納棺式、10時30分から12時まで葬儀と初七日、火葬場へ移動し12時30分から14時まで火葬と収骨を行い、14時30分頃には解散。火葬時間や移動距離は故人により異なりますが参考にしてください。
一日葬はどんな人に適しているか
一日葬は通夜を行わない分、喪主の負担を抑えた葬儀形式です。1日で終了でき時間を有効活用できるため近年増えています。では一日葬はどのような方におすすめなのでしょうか。一日葬に適している場合と行わない方がいい場合を解説します。
一日葬が適しているケース
・遠方から親戚が来る場合
通夜を行う場合、遠方の親戚の宿泊先を手配する必要があります。斎場内の控室は家族の付き添い用の意味合いが強く親戚を宿泊させるのにあまり適しません。一日葬であれば当日の朝出発し、その日のうちに帰宅することも可能です。
・高齢の親族が来る場合
通夜と葬儀の両方に参列するのは高齢者にとって体力的に負担が大きいと言えます。通夜振る舞いに参加すると散会時間が20時を回ることもありますので、帰るころには深夜になってしまうこともあります。一日葬なら朝から夕方まで約5~6時間で終了するスケジュールですので体力的な負担が少ないと言えます。
・菩提寺がない場合
お寺を葬儀社に紹介してもらう場合、1日と2日とでお布施の金額が異なります。費用負担を減らしつつ、お経をあげてほしい場合は一日葬が適しています。依頼先によって異なりますが7万円~10万円程度抑えることが可能です。
一日葬が適さないケース
・一般参列者が多い場合
一般参列者が多い場合は通夜を行った方が良いと言えます。一日葬だとすべての参列者が1日に集中するため通夜を行うよりも慌ただしくなります。特に葬儀は出棺まで参列者が帰らないので静かにお別れする時間が取りにくくなります。また、仕事をしている人は日中行う一日葬に参列できません。そのため、安置中や葬儀後に弔問客の対応に追われなかなか落ち着かないという方も多いです。
・菩提寺がある場合
厳格な菩提寺の場合、一日葬を認めていただけない場合があります。本来行うべき通夜の勤めを割愛することを嫌うからです。儀式をつかさどるのは導師を勤める菩提寺ですので、儀式の進め方は菩提寺の意向で決定します。最近は一日葬が増え、家族が希望すれば認めてくださる場合もありますが、必ずお伺いを立ててから一日葬を行うようにしましょう。
まとめ
一日葬の流れとスケジュールについて解説いたしました。一日葬は通夜を行わない分、喪主や参列者の負担が少ない形式だということがわかりました。所要時間は約5~6時間とやや長めにはなりますが夕方には自宅に帰れることが一般的です。さらに時間を短縮したい場合は納棺式のみ前日に前倒して行うことも可能です。ただし、参列者が多い場合や菩提寺がある場合には十分に考慮する必要があります。安易に一日葬を選択するとかえって後悔することになりかねません。家族と相談して後悔のないお葬式を行いましょう。
葬儀のセカンドオピニオンでは後悔しないお葬式のサポートの一環として、葬儀社の情報収集代行と比較検討のアドバイスを行っています。一度お気軽にご相談ください。